難民支援協会(JAR)の活動は、難民スペシャルサポーター(毎月の寄付)を含めた寄付者やボランティアなどの皆さまからの支えで成り立っています。「わたしと難民支援」ではそんな支援者の思いをお届けします。
今回は、小林 秀男さん(自営業/2020年から難民スペシャルサポーター)より寄稿いただきました。
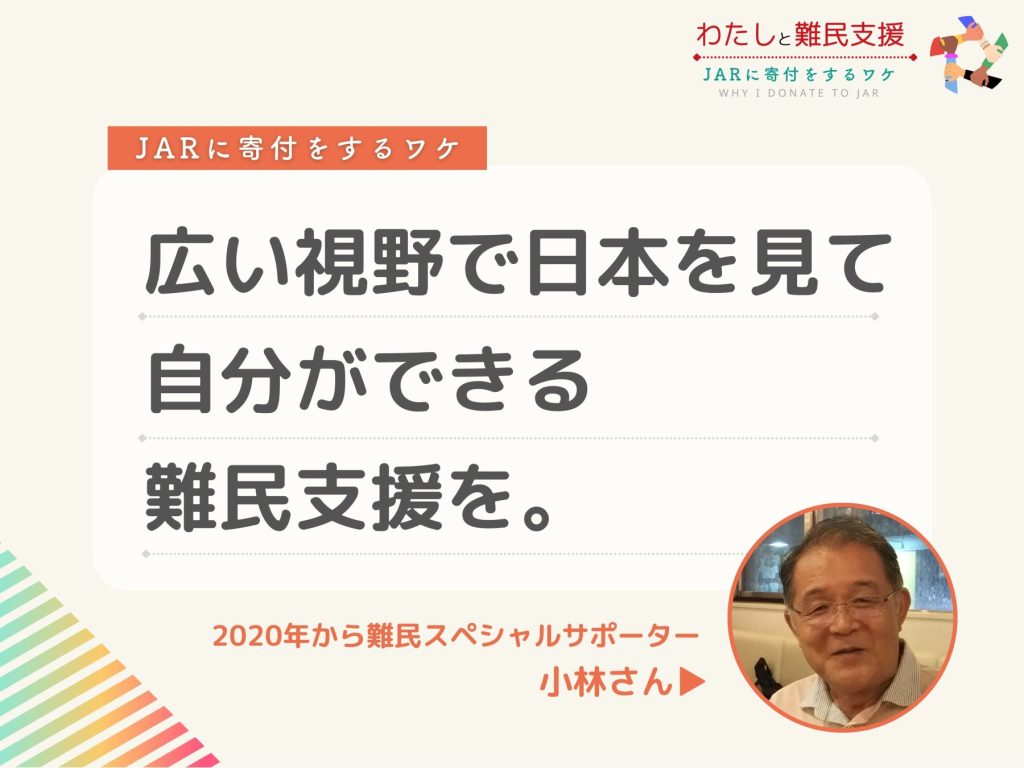
寄付のきっかけは、シリア難民のルポ書籍
私は自営業で税金や社会保険にかかわる仕事をしています。難民の方々を支援する活動に参加したいと思いながら、いつも自分のことに精一杯で、申し訳ないと思っています。
「難民問題」に関心を持ったのは、8年ほど前に英国ガーディアン紙の記者が書いた『シリア難民』という本を読んだことがきっかけです。シリアや中近東・アフリカからヨーロッパに逃れる難民に同行したレポートとEUの政治情勢などをカバーしたルポルタージュです。欧州に何百万人もの難民や移民が流れ込んで、難民危機といわれた時期です。一方、難民の適切な受け入れができておらず、難民に極めて厳しい日本ですが、その中でも日本に逃れてきた難民のために活動している難民支援協会のことを知り、自分ができる応援をしたいと思いました。
世論調査では難民の受け入れについて否定的な結果が出たりしますが、海外で難民が急増したり、テロ事件が起きたりしたときに調査が行われるので、そういう傾向が出るようです。私が周囲と個人的に話をすると、難民に同情的で何とかしてあげたいという人が多いです
難民問題を通して見える日本の姿とNPOの存在意義
自国の国境管理の実情というのはその国の人には見えにくく、むしろ外国から見たほうがよくわかるものです。私の実体験でも、ほかの国の人も自分の国のことはわかっていないなあ、と感じたことがあります。そういう意味で、「難民問題」は日本という国を映す鏡であるといえます。
国境管理をしている入管庁(出入国在留管理庁)が難民認定をしていること、難民申請者や非正規滞在者の扱いが極めて非人道的であること、そして人権より「外交関係」に配慮した対応がみられることなど、「難民問題」に限ったことではありませんが、鏡に映った日本は、人権という観点からみると誠に醜い顔をした国と言わざるを得ません。
政治的なリーダーシップが求められますが、難民と国家というのはどうしても相容れない面があります。そこに難民支援協会をはじめとするNPOの存在意義があると思います。

![[冬のご寄付のお願い]「明日はどうなるのか」「今日はどこで寝られるのか」先の見えない不安の中で、支援を必要としている難民がいます。](https://www.refugee.or.jp/wp-content/uploads/2024/11/dc_2024w_bnr.png)

![東京マラソン2026チャリティについて 認定NPO法人 難民支援協会は、東京マラソン2026[2026年3月1日(日)開催]チャリティに寄付先団体として参加いたします。](https://www.refugee.or.jp/wp-content/uploads/2025/03/3384fa5665ae072e1cf93e3aff72d4b3-80x80.jpg)







