
昨年5月、数千人にのぼる人々を乗せた複数の木造船が海上で漂流を続けた。密航業者は逃亡し、残された乗客が接岸を試みると押し返され、行く先を失った。食糧が尽き、多くの人が船内で亡くなった。これは地中海の出来事ではない。東南アジアでロヒンギャ民族を襲った悲劇だ。ロヒンギャはミャンマー(ビルマ)のラカイン州北西部に暮らす少数民族だが、ミャンマー政府はバングラデシュからの不法移民だとして、長らく迫害してきた。特に1982年の国籍法改定以降は公民権もはく奪した。耐えかねた人々が船でタイ、マレーシア、インドネシアを目指すようになったが、どの国からも受け入れを拒否され、かといって帰る場所もなく漂流を余儀なくされた。マレーシアとインドネシアが漂流中のロヒンギャに限って、一年以内の帰還を条件に受け入れたが、ロヒンギャを取り巻く状況は改善されないまま、期限が近づいている。ゾーミントゥさんは、取り残された同胞たちの力になるべく、日本から休みなく活動するロヒンギャの一人だ。「贅沢や遊びには興味がないんです。ロヒンギャや、かつての自分のように苦しむ日本の難民たちのため、できることはすべてしたい」と話す彼の信念は固い。
ビルマ名「ゾーミントゥ」での出国
ゾーミントゥさんはロヒンギャのなかでは裕福な生まれで、ヤンゴン大学で科学を専攻した後、大学院に進学した。当時の軍事政権は民衆を徹底的に弾圧し、ロヒンギャに至っては強制労働に従事させたり、移動制限を課したりと、深刻な人権侵害を日常的に行っていた。そうした苦境からロヒンギャを解放するには、軍事政権を変えるしかないと考えた彼は、アウンサンスーチー氏が自宅軟禁から解放された95年から民主化運動に参加するようになったという。学生運動は大規模化し、大学は閉鎖。沈静化を図りたい政府は、中心メンバーたちの自宅を回り、次々と逮捕していった。政治犯として拘禁されれば、釈放は望めない。捕まった友人の母親から「政府があなたの居場所を聞いて回っている」と連絡が入り、郊外で3か月間潜伏。いつまでもは隠れられないと危険を感じ、ブローカーを通じて出国を手配した。
「ゾーミントゥ」は本名ではない。政府が捜索中のリストに名前が入っていた上、ロヒンギャと分かるイスラム名では空港で止められるため、ビルマ名も登録し、そのパスポートを使って来日した。今でもイスラム名を名乗ることはないという。ブローカーが手配したのは商用ビザ。しかし、学生に見えたためか、成田空港の入国審査で止められ、上陸拒否されてしまう。日本で難民申請できることは知っていたものの、母国への送還が怖く空港で申し出ることはためらわれた。
弁護士ワタナベと戦った4年間
空港の施設に留め置かれ、いつ送り返されるかと怯えていると、電話がかかってきていると呼び出された。
「弁護士のワタナベです」
数年前に日本へ逃れた叔父が、ミャンマーに残る叔母より彼の来日について聞き、到着の連絡がないため心配して渡邉彰悟弁護士に相談したという。渡邉氏は1992年に在日ビルマ人難民申請弁護団を立ち上げ、弁護士として数多くの難民申請者を支援してきた。電話越しにいくつか質問され、最後にこう聞かれた。「Are you a refugee?(あなたは難民ですか)」。入国管理局(以下、入管)の職員を前に答えていいのか。この弁護士は味方なのか。2回沈黙した。しかし、叔父の紹介は信じていいはずだ。3回目でようやく「Yes」と答えた。勇気のいる告白だった。
その後、難民申請書が用意され、入管職員を前にして書き進めた。軍事政権下のミャンマーでは、何も落ち度がなくても、警察を見たら逃げるのが常識というほど政府関係者は警戒すべき存在だ。ゾーミントゥさんは日本の事情が異なることを知らず、制服を着た人を心底恐れていたという。苛立つ職員の様子も相まって、すっかり気が動転してしまい、両親の名前も書き間違えてしまうほどだったと当時を振り返る。申請を終えても収容は続いた。一体どうすれば外に出られるのかと途方に暮れているとUNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所職員が面会にきた。権威ある国際機関の登場に期待したが、かけられたのは意外な言葉だった。
「あなたをここから出せるのは、いま日本で渡邉弁護士だけ。彼はやると決めたら絶対にやる人。彼を信じて頑張って」面会にきた渡邉弁護士はまだ若く見え、正直不安に思っていたが、その言葉に後押しされて、彼にすべてを話そうと決めたという。
 まもなく茨城県牛久の収容所に移送され、早々に言い渡されたのは難民不認定の結果。異議申し立ての面接では、渡邉氏がある映像を証拠の一つとして持参していた。自身も参加した96年の大規模学生デモの様子がモニターに映し出された。目の前で友人たちを亡くした記憶がよみがえり、こらえきれずに号泣した。「この姿を見てまだ難民ではないと思いますか?」と渡邉氏は審査官に詰め寄った。
まもなく茨城県牛久の収容所に移送され、早々に言い渡されたのは難民不認定の結果。異議申し立ての面接では、渡邉氏がある映像を証拠の一つとして持参していた。自身も参加した96年の大規模学生デモの様子がモニターに映し出された。目の前で友人たちを亡くした記憶がよみがえり、こらえきれずに号泣した。「この姿を見てまだ難民ではないと思いますか?」と渡邉氏は審査官に詰め寄った。
異議の結果を待つ間にようやく「仮放免」となり、収容所から解放された。来日して11ヶ月と5日。誕生日が前日だった渡邉氏は誕生日プレゼントだと一緒に喜んだ。しかし、安心した矢先の通知は、またしても不認定(異議申立の棄却)。最後の可能性にかけて裁判を起こした。絶対に勝つと、渡邉氏はビルマ研究者などからも協力を得て徹夜をいとわず臨んでくれたという。いよいよ判決がでる2週間前に入管から届いた一通の手紙には、不認定を取り消す旨があっさりと書かれていた。裁判に費やした労力を思うと釈然としない認定だ。「勝訴という結果が残ることを恐れての決定としか思えなかった。嬉しかったけれど、なぜ4年もかかったのだろうという思いは消えません」と話す。
同胞のための闘い
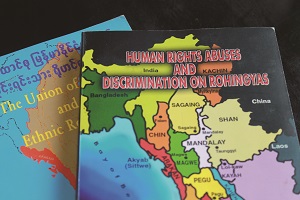 六本木のレストランで皿洗いを8年続けて生活が安定し、ミャンマーで暮らしていたロヒンギャの女性と結婚。日本へ呼び寄せた機会に、家賃の安い群馬県に引っ越して工場で勤務した。11年間貯金した資金を元手に、リサイクル会社を興して7年になる。3人の息子に恵まれ、平穏な日々を送れるようになったが、ゾーミントゥさんの闘いは終わらない。少しでも時間があれば、ミャンマー国内のロヒンギャから相談を受け、それをもとに日本の国会議員へロビイングを行ったり、ロヒンギャの窮状を訴える本を書いたりと身を削って活動している。携帯には日々、海外にいる仲間たちから連絡が入る。「一人のロヒンギャとして、できることがあるなら何でもしたい。いまこうしていられるのは、僕が偉いからじゃないんです。渡邉先生だけでなく、通訳の人、JAR、UNHCR、僕を雇ってくれた会社など、数えきれない人の助けがあって、一緒に頑張ってくれたから。それをいつも思い出しています。ロヒンギャだけでなく、日本の難民たちが同じように助けられるまで、できることをしたい」と活動にかける思いを話してくれた。
六本木のレストランで皿洗いを8年続けて生活が安定し、ミャンマーで暮らしていたロヒンギャの女性と結婚。日本へ呼び寄せた機会に、家賃の安い群馬県に引っ越して工場で勤務した。11年間貯金した資金を元手に、リサイクル会社を興して7年になる。3人の息子に恵まれ、平穏な日々を送れるようになったが、ゾーミントゥさんの闘いは終わらない。少しでも時間があれば、ミャンマー国内のロヒンギャから相談を受け、それをもとに日本の国会議員へロビイングを行ったり、ロヒンギャの窮状を訴える本を書いたりと身を削って活動している。携帯には日々、海外にいる仲間たちから連絡が入る。「一人のロヒンギャとして、できることがあるなら何でもしたい。いまこうしていられるのは、僕が偉いからじゃないんです。渡邉先生だけでなく、通訳の人、JAR、UNHCR、僕を雇ってくれた会社など、数えきれない人の助けがあって、一緒に頑張ってくれたから。それをいつも思い出しています。ロヒンギャだけでなく、日本の難民たちが同じように助けられるまで、できることをしたい」と活動にかける思いを話してくれた。
申請の結果が出るまでに要する時間の長さ、その間の生活保障の不足、増えない認定数―。難民にとって希望の見えない状況がずっと続いている。「日本はいい心を持っている人が多いです。よくならないのは、ただ知らないからではないでしょうか。元気なときに病気のことを考えない。それがいまの日本かなと思います。でも、元気なときこそ勉強してと伝えたい。日本に逃れてきた難民が人間らしく暮らしていくために、一人ひとりにできる支援があることを知ってもらえたら」とゾーミントゥさんは指摘する。
世界の紛争や人権侵害の根を止めることは一国の努力だけではできない。しかし、日本にたどり着いた難民の命を救えるのは日本にいる私たちだ。送り返される不安を抱えながらも必死に暮らす人たちの未来を閉ざすのか、あるいは彼/彼女に安全を提供し、よりよい社会をともに作っていくのかは、私たちが選択できる。
ロヒンギャ難民についてはこちら





