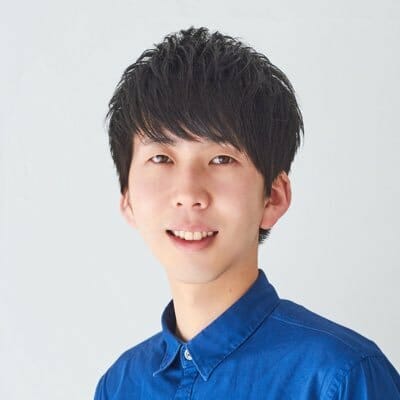2019.06.06
ただ世界でたった一人の「家族」と一緒にいたかった。台湾と日本、結婚できない「二人の男性」が辿り着いた場所
桜もピークを過ぎ、少しずつ散りはじめてきた4月中旬。私は千葉県内のとある駅の改札でその人と落ち合った。Gさんだ。

マスクをしたGさんは「花粉がひどくて」と言った。1969年に台湾の台北市で生まれ、今年で50歳になる。Gさんはゲイで、HIV陽性者でもある。
幼少期に自身がゲイであることを自覚した彼は、そのコンプレックスから何度も自殺未遂を繰り返し、家族とも疎遠になった。
1992年、23歳のときに逃げるように台湾を離れた彼が留学生としてやってきたのが日本だった。
1993年に再び観光ビザで日本にやってきた際、現在のパートナーである日本人のYさんと出会い、1994年にもう一度観光ビザで日本へ。それ以来、今までずっと日本で暮らしている。

90年代半ばに2度目の観光ビザが切れたあとも日本に残ることを選んだGさんはいわゆる「オーバーステイ」の状態になった。つまり、彼は長い間在留資格を持たない「非正規滞在者」だったのだ。
異性のカップルであれば結婚して配偶者のビザを得る道もあっただろう。しかし、同性であるGさんとYさんにはその道は閉ざされていた。
その後二人は世間の目を避けるようにひっそりと暮らしていくことになるが、のちにGさんがHIVに感染していることも発覚する。体調は悪くなる一方だった。
転機が訪れたのは2016年。新宿の路上で職務質問を受け、オーバーステイが発覚した。Gさんは強制退去を命じられてしまう。
翌年、Gさんは強制退去の取り消しを求めて国を提訴した。「ただ大切なパートナーのYさんと一緒に日本で生きたい」その一心で。

Gさんは非正規滞在者「だった」と書いた。
そう、今年3月15日に国はGさんの強制退去処分を取り下げ「在留特別許可」を認めたのだ。日本で国際同性カップルの一方に在留特別許可が出たのは初めてのことだ。一審の判決が出る前のことだった。
Gさんはようやく正規の在留資格を得た。そして、再び千葉でYさんと暮らしている。繰り返すが、GさんとYさんが異性のカップルだったらこういう25年間にはなっていなかっただろう。
在留資格のない国際同性カップルとして、GさんとYさんは日本でどんな思いで過ごしてきたのか。二人にとって「家族」とは何なのか。それぞれの人生を振り返りながら、いまの率直な思いを聞かせていただいた。

同性愛の自覚
――Gさんは自分がゲイであることを自覚したのはいつですか?
Gさん:小学生のころでした。きっかけは、同級生の男の子が気になるようになったことです。「同性愛者」という言葉を知ったのは高校に入ってからで、当時は「社会的に認められない、いけないことなんだ」と思っていました。
でも思春期だったので、どうしても同性に対する関心を止められませんでした。当時は携帯電話もネットもなかったので、雑誌で知ったゲイが集まるスポットに夜な夜な行っていました。
――Yさんはいかがですか?
Yさん:僕は中学1年生のときでした。実家がある北海道の中学校に通っていたんですが、きっかけは特になくて。「ああ、僕は女性より男性が好きになるんだな」と自然と気がついた感じです。
当時は間抜けな性格だったのもあり、すんなり自分のことを受け入れられました。でも、クラスの男子から「男が好きなのは“ホモ”って言うんだよ」と言われたことがあって、今でもこの言葉を覚えています。特に悩むことはなかったので、家族や友人にカミングアウトする必要性も感じていませんでした。

――Yさんはいつ頃東京に上京されたのですか?
Yさん:高校を卒業してすぐに上京して一人暮らしをはじめました。最初は普通に就職したんですが人間関係がうまくいかず半年くらいで辞めてしまいました。ちょうどバブルが終わった頃です。
その後は時給に惹かれてホテル関係の派遣の仕事をしていたのですが、その頃から性格がだんだんネガティブになっていきました。理由は、自分が「派遣で働いている」ということに対してコンプレックスを抱くようになったからです。
コンプレックスが大きくなる一方で、自分が正社員として働ける可能性は少しずつ狭まっていく。そのことに負い目や引け目を感じて、人に会いたくなくない、喋りたくないと思うようになっていったんです。
自殺未遂、カミングアウト、軍からの除隊
――Gさんは家族や周りの人にはカミングアウトされていますか?
Gさん:していません。私が生まれたのは1969年の台湾台北市で、家族構成は自分も含めて9人。上から7番目の5男でした。

17〜8歳の頃にアメリカからの留学生と2年間付き合ったのですが色々ありました。「同性愛は反社会的だ」と自分自身もゲイに対してのコンプレックスがあり、精神的に不安定になり、うつの症状もありました。
自殺願望が強く、睡眠薬やリストカットなどで自殺未遂を繰り返しました。ゲイであることを誰にも言えなかったし、ましてや相談なんて全くできませんでした。
――自殺未遂を何度も…。
Gさん:当時台湾では20歳になると兵役の義務があったのですが、18歳から兵役を迎えるまでの2年間、何度か自殺未遂を繰り返していました。
最初に睡眠薬を使って自殺を図った時、家族が病院にかけつけてきて、そのとき伝えようと思ったのですが、姉から「同性愛の病気が治ったら家に帰ろうね」と言われました。
結局自分からはカミングアウトできなかったんですが、その後も自分がゲイであることを家族に伝える機会はありませんでした。

そのあと1989年に20歳で軍隊に入ったのですが3ヶ月で除隊させられました。その理由は「同性愛者」だから。理由について家族には直接伝えていませんが、薄々気づかれていたのではと思います。
――同性愛が除隊の理由だったんですね…。
Gさん:兵役につく前に過去の経歴や病歴などの身辺調査をされるのですが、やはり自殺未遂の理由について聞かれました。過去のカルテを元に問い詰められて同性愛について伝えたところ、さらに根掘り葉掘り聞かれました。やむを得ず全て答えました。
軍の人は驚いていました。軍の病院に連れて行かれ「本当に同性愛者なのか、うつ病なのか確かめる」と精神鑑定を受けさせられました。
――どうやって調べたのですか?
Gさん:図形のようなものが目の前に並べられて「どういう気持ちになりますか」と聞かれましたね。今考えると、なぜ図形を見ただけでゲイかどうかわかるのか疑問ですが。直接的なものでは、エロ本を置かれて「どういう気持ちになるか」ということも聞かれました。
結果、書面にはうつ病のことは書かれず「この人は同性愛者です」と書かれていました。同性愛者であることを理由に3ヶ月で軍隊を辞めさせられたんです。

来日、新宿二丁目での出会い
――Gさんが日本に来たのはいつですか?
Gさん:1992年に1年間の語学留学で来日しました。10代の頃から外国語に興味があって日本語を勉強し始めました。将来は人と接する職業に就きたいと思っていたんです。
――Yさんと出会ったのはいつですか?
Gさん:日本語能力試験を受験するために観光ビザで再び来日した1993年の11月です。
試験は落ちてしまったのですが、新宿二丁目のゲイバーで彼と出会いました。僕が23歳、彼が32歳の頃でした。
寡黙で優しそうな人だなと思い、僕が片言の日本語で話しかけ積極的にアプローチしました。その後付き合うことになり、1994年の1月から一緒に暮らしはじめました。

――YさんにとってGさんの第一印象はいかがでしたか?
Yさん:当時は派遣という仕事をおおっぴらに誰かに言えるようなものではないと思っていたので、自分からアプローチして誰かと付き合おうという気持ちはありませんでした。
人と会うのが嫌で、新宿二丁目にも滅多に行っていなかったんです。(Gさんと出会った)その夜は多分寂しくてたまたま行きたい気分になったんだと思います。
でも彼と出会い、なついてきたので付き合うことになりました。外国人であることは特に何も気にならなかったです。たまたま出会ったのが彼だったというだけで、そこから気づいたら25年も経ちましたね。
「オーバーステイ」の選択
――Gさんがオーバーステイになったのはいつですか?
Gさん:1994年の4月です。それまでは3ヶ月の短期滞在の在留資格で日本に来ていたのですが、「彼と一緒にいたい」と思ってオーバーステイになっても良いか彼に相談しました。でも最終的に決めたのは僕自身です。

――YさんはGさんから相談されたときどう思いましたか?
Yさん:残るか残らないかは彼の自由だし、自分から「残りなさい」とは言いませんでした。彼のその後の人生に責任を持つことはできないから「自分で決めてください」と。
――Gさんはなぜオーバーステイを選択したのですか?
Gさん:台湾で生まれてからずっと「同性愛者はいけない存在だ」という考えが頭の中にあって、日本に来てもその気持ちは消えませんでした。
80~90年代のゲイカップルの関係は、結婚して子どもを育てることもないし、長く続かないと言われがちでした。もし彼と別れて台湾に帰ったら、僕はまたひとりぼっちになってしまう。
これから僕と彼が何年関係を続けられるかはわからないけど、もし彼が良かったら、一緒に生きていきたいなと思ったんです。オーバーステイになることはすごく悩みました。でも僕はこの縁を切りたくないと思ったんです。

――そこからGさんのオーバーステイが発覚するまで22年間、お仕事はどうされていたのですか?
Gさん:生活のために彼はホテルの配膳など、自分は結婚式場の厨房の食材仕込みや洗い場、ホテルの客室の清掃など色々な仕事をしました。
実は10数年間、職場では彼の苗字を名乗っていました。日本人の名前の方が仕事に就きやすかったから。もちろんダメなことなのですが、当時は身分証の確認もほとんどなく、彼と生きていくためにそういう手段を選ばざるを得ませんでした。
同僚に疑問に思われたら「ハーフです」と言ってごまかしたりしていました。日本人のふりをしたかったというのもありました。10代の頃の自殺未遂や家族との関係が辛くて、当時は台湾にいた時の過去を忘れたいという気持ちでいっぱいでした。
HIV感染の発覚
――GさんのHIVの感染が発覚したのはいつ頃でしたか?
Gさん:彼と付き合って1年が経った頃でした。なかなか風邪が治らないので検査したところ感染していることがわかりました。「このまま日本で死ぬのかな」とかなり絶望的な気持ちになりましたが、それでも「死ぬなら日本で死にたいな」という気持ちがずっとありました。

――Yさんはどう受け止めましたか?
Yさん:しょうがないという気持ちしかなかったです。もちろんびっくりはしましたが。今更放り出すわけにもいきません。
――治療や薬はどうしていたのですか?
Gさん:健康保険に入れなかったので抗HIV薬は飲まず、対症療法で対応していました。咳がひどいときは咳止めを飲んだり。何も症状が出ない安定期もあったのですが、そういう形がズルズルと2004年頃まで続きました。
症状が悪化しはじめた頃に駒込病院の方からHIV陽性者の支援を行っている「ぷれいす東京」というNPOを紹介してもらったのですが、最初は断ってしまいました。
――どうして断ったのですか?
Gさん:症状が悪化して死んでしまう心配もありましたが、それよりも身分がバレて台湾に送還されることへの恐怖のほうが強くありました。ただ、やはりその後ぷれいす東京に事情を話し、海外から抗HIV薬を入手していただくことになりました。
台湾はHIVやエイズに関して無料でサポートを受けられる医療体制があって日本より進んでいましたが、日本では検査や薬は自費ですし海外からの薬もいつまで入手し続けられるかわからない。だから、ぷれいす東京の生島さんや、生島さんから紹介いただいた「港町診療所」(神奈川県勤労者医療生活協同組合)所長の沢田先生からも「台湾に戻った方が良い」と言われました。

それでもやっぱり日本に残りたいという気持ちが勝って「薬が切れても日本にいたい」と思っていました。この気持ちは彼と付き合い始めたときから今も変わっていません。そこから10数年、生島さんや沢田先生のおかげで容態は安定していました。お二人がいなければ私は今ここにいません。
――Yさんの生活にも何か変化がありましたか?
Yさん:2007年に働いていた先が違う業者と契約してしまい、僕たちは撤退することになってしまいました。その後両親が亡くなってしまい転職活動はしませんでした。抑うつ的になって、新しいことに挑戦するのが難しくなっていたというのもありました。
――その後はYさんのご両親が残されたお金とGさんの収入で暮らしていたんですね。
Gさん:はい。自分はホテルの客室掃除の仕事を10年以上やっていたのですが、やっぱり20代の子に混ざって仕事をすることが体力的に限界になってきていました。体調が不安定な時期もあり、二人とも年を取ってきてお金もギリギリでした。ぷれいす東京に相談して、ゲイをオープンにされている永野弁護士と、山下弁護士・森弁護士につないでいただいたのが2013年のことです。

突然の出来事
――それから在留特別許可を求める準備を始めたんですね。入管に出頭すると働くことは難しくなると思うのですが、その辺りはどうされていたのですか。
Gさん:すぐに出頭するわけではなく、まずは永野弁護士たちから家計簿をつけるように言われて、仕事を続けながら生活を切り詰めて準備のためにお金を貯めていきました。
しかし、それから3年後の2016年の6月16日のことでした。新宿の世界堂の反対側のドトールのある交差点で、突然若い警察官に後ろから肩を叩かれて「身分証明書をお持ちですか」と聞かれてしまったんです。
――オーバーステイが発覚してしまったのですね。
Gさん:あの日はたまたま仕事が早めに終わって、少し時間があるから「ビックロ」に家電を見に行こうとしていたところでした。職務質問をされたことは23年間で一度もなかったのですが、服装があまり綺麗じゃなかったからかもしれません。普段は警察が近くにいたら避けるようにしていました。なぜこのタイミングだったのか…。
――そのときは職務質問にどう答えたのですか?
Gさん:「私は身分証明書を持っていません」と、そのまま自供です。「じゃあ、あなたはどの国の人ですか?」と聞かれて「台湾出身です」と答えました。そうすると「あなたはオーバーステイですか?」と聞かれて「そうです」と。

それからパトカーが呼ばれ、中で持ち物を全部調べられた後、四谷警察署まで連れていかれました。夕方の16時頃だったかと思います。
その後、深夜1時頃まで取り調べを受けました。永野弁護士たちに「この人は在留特別許可の申請中です」と説明する用紙まで作ってもらっていたのに、あの日は持っていなかったんです。警察にその紙のことを伝えても言い訳としか受け取ってもらえませんでした。
――その後はすぐに入管へ移送されたのでしょうか。
Gさん:いえ、深夜まで続いた取り調べの後に(四谷警察署から)原宿警察署に移されて20日間ほど拘留されました。その後、品川にある入国管理局に移送されました。
――HIVの薬は毎日服薬しなければいけないと思いますが、原宿警察署や入管では薬を入手できましたか?
Gさん:原宿警察署では自分がHIV陽性者であることを伝えたら、翌日に手錠と腰に縄をかけられ、新宿駅の東口にあるクリニックに行って診察を受け、HIVの薬を出してもらいました。でも、その薬が体に合わなくて、取り調べの間に14回ぐらい下痢をしてしまいました。
それで、本当はダメなのですが、勝手に薬の服薬を止めて体調を落ち着かせました。入管の方では入管所属の医師の方に改めて診察していただき、HIVの薬を処方してもらいましたが、そちらの薬は大丈夫でした。

入管施設での収容
――入管の施設はどういった状況でしたか?
Gさん:だいたい4〜5人が相部屋になっていることが多いのですが、自分は独房でした。多分、同性愛者でHIV陽性者だから。4畳くらいのスペースにトイレがあるだけ。自分は周りに誰かがいると気になってしまうので、かえって独房でよかったです。
それでも、収容された場合は強制送還されてしまう場合もあると入管職員から何度も聞かされていたので、もしそうなったら死ぬしかないと本気で思っていました。
――そうだったんですね…。
Gさん:入管に移送されてすぐに「チケット係」と呼ばれる20代後半くらいの制服を着た男性の入管職員がやってきて「日本は同性婚がないから裁判しても勝ち目はないですよ。早めに台湾に帰る準備をした方が良い。台湾なら片道5万円です」と言われました。今でもはっきり覚えています。

チケット係との接触があったのは2回で、もう1回は在留特別許可が認められず、退去強制令書を出されたときでした。ガタイの良い二人の入管職員が突然個室に入ってきて、「すぐに台湾に帰りなさい」と言いました。
強制退去の命令が出た途端に暴れ出すと思われていたようですが、自分もある程度予想できていたのと、永野弁護士や山下弁護士との面会をして在留特別許可を求める裁判の準備もしていたので「これで終わりじゃない」と思い、冷静でいられました。
――心は決まっていたのですね。
Gさん:入管職員の方々は立場上「国に帰れ」と言わざるを得ないと思います。二人の職員に何度も「台湾に帰った方が絶対良いです」と言われ、自分は「帰りません、裁判の準備の真っ最中です」と答え、シーソーゲームのような状況でした。
2013年に永野山下法律事務所に相談に行ってからずっと在留特別許可の申請の準備をしてきたのに、それが無駄になってしまう。絶対に負けられないと思いました。入管職員からの暴力はなかったですが、言葉の圧力を感じ、その1時間はこれまでで一番しんどかったです。
――Yさんは、Gさんが警察に捕まったのを当日どう知ったのですか?
Yさん:確か彼が警察に捕まった日の翌日は彼の仕事が休みだったので、どこかフラフラしてるのかなと思っていました。でも21時頃になっても全然帰ってこないから「何やってるんだろう」と思っていたところ、22時半くらいに突然警察から電話がかかってきて彼が捕まったと聞きました。

翌日、永野弁護士と山下弁護士の事務所に行き、着替えなどを持って警察署にも行ったのですが、彼が体調不良で会えませんでした。
――これまでも「いつかGさんが捕まってしまうかも」という不安や懸念はありましたか?
Yさん:はい。でもこれから裁判をすると準備をしていて、自分がリスクを抱えて生活をしている最中に、大した用事もないのに新宿をフラフラしていたことに僕は腹がたちました。正直、今でも許せないです。
今回の裁判はたまたま良い結果をいただけたけど、そうならない可能性もありました。僕以外にもいろいろな人に迷惑をかけています。だから、原宿警察署で面会した時はとても怒りました。今でもこれについては怒っています。
仮放免と困窮の日々、そして裁判へ
――Gさんが収容されて約1ヶ月後に仮放免の許可が降りたのですね。
Gさん:仮放免されたのは2016年の7月22日でした。家に帰っても仕事をすることは許されていないので、少しの貯金を切り崩しながら生活していました。
翌年の1月には貯金が無くなりそうになってしまい、これからどうしようというときに、山下弁護士を通じて、とある個人からご支援をいただきました。その後も多くの支援者の方々からご支援をいただき、2017年1月には第1回目の支援者の会を開催していただきました。それが、僕が日本のLGBT関連の団体と初めて接触した機会でした。

――クラウドファンディングでGさんの訴訟への支援を募る動きもありましたね。
Gさん:2月にぷれいす東京の生島さんに明治大学法学部教授の鈴木賢先生をご紹介いただき、鈴木先生がクラウドファンディングを使って支援金を集めてくださいました。今でも本当にお世話になっています。
いろんな方々からご支援をいただきましたが、やはり毎日が不安続きでした。これから裁判がどれくらい続くのか、支援者の方々からの支援が続くのかどうか、自分の薬をどうしようか。
仮放免中は働くこともできないですし、移動も自由にできません。ですが、それよりも自分がこういう風に生活をしていることで周りの人に迷惑をかけているという自覚と不安の方が大きかったです。今も申し訳ないと思っています。
――働けないのは経済的にかなり厳しいですね。
Gさん:在留特別許可が降りるまでの約2年半、服がボロボロになっても新しいものは買えませんでした。テレビは壊れていたので我慢したり、携帯電話も無くしてしまって古いタブレットを使っていました。靴下も穴が開いても履き続けていました。
この部屋のカーテンも買い換えられないので、ガムテープを使って破れたところを止めています。

――その後訴訟はどうなったのですか?
Gさん: 2016年11月に退去強制令書の発付処分を受け、2017年3月にその取り消しを求めて提訴しました。
3月21日の朝日新聞で取り上げていただきましたが、ネットでは「台湾に帰れ、このエイズ野郎」というコメントなど、色々な反論が1000件以上あり、難しい裁判をするしかないんだなと思いました。
一方で、支援者の方々も増えました。「不法滞在」の同性カップルでHIV感染者だし、世間的にはマイナスなイメージの方が多いと思います。それなのに応援してくれる人たちがいて、感謝の気持ちでいっぱいです。
ネット上のネガティブなコメントの多く想像はできますが、できるだけ考えないように、見ないようにしていました。
――もし訴訟で負けたらどうするか考えていましたか?
Gさん:何年かかっても最高裁までいく覚悟はありました。あらゆる手段を尽くしたいという強い意思もありましたが、もしそれでも負けてしまったら、それはもう死ぬしかないなとも思っていました。

裁判の結果
――Yさんは、Gさんが裁判をすることについてどう考えていましたか?
Yさん:応援してくれた人たちに申し訳ないのですが、正直な気持ちとしては「ほんとに勝てるのかな」と思っていました。静かに隠れて暮らした方が良いのではないかと。
オーバーステイになったことは、彼が自分で決めて僕はそれを受け止めただけなので、そんなに深く考えず、20数年間、二人でそれなりに楽しく過ごしてやってきました。
表に出て行ってもし裁判に負けたら、失うものが大きい。今回はありがたい結果になったけれど、正直な気持ちとしては裁判をすることはとても不安でした。だって僕たちみたいな一個人がコネや大金を持っているわけでもないのに、国を相手に裁判をして「勝てるのかな」と。
――それでもGさんの決断を尊重されたんですね。
Yさん:裁判がうまくいかなかった場合のことは考えないようにしていました。始まったものは後戻りできないから。あとは弁護士の先生方や支援者の方々を信じて、任せるしかないと思っていました。
彼が捕まる前だったら裁判をすること自体も悩みましたが、もう捕まってしまったのでやるしかないという状況でした。

――最終的には、裁判の判決が出る前の今年3月15日に在留特別許可が出たんですよね。本当におめでとうございます。
Gさん:弁護士の皆さんや支援者の方々、メディアの方々に大きな力をいただいて、本当に感謝しきれない思いです。自由を手に入れることができて、これからどうやって生活するかを毎日考えています。まずは早く仕事を見つけて生活を安定させたいです。
在留特別許可が出たことについては日本政府に非常に感謝しています。でもそもそも「なぜ同性どうしの結婚がダメなのか」ということについては疑問に思っています。
日本でもたくさんの同性カップルが「同性婚が認められないことは憲法違反だ」として全国で国を一斉提訴しましたが、自分も心は彼らと共にあります。
――今改めてオーバーステイをした自分の決断をどう思いますか?
Gさん:オーバーステイになったときに「自分にはもう明るい未来はない」と覚悟はしていました。でもこの選択を後悔はしていません。大変だということはわかってはいたけれど、でも彼と一緒にいれば乗り越えられるという覚悟がありました。

「家族」とは何か
――お二人にとってお互いはどういう存在ですか?
Gさん:自分は10代の頃からゲイであることを理由に悩み、何度も自殺未遂をしました。結局、家族としっかり話し合う場もないまま日本に来て、もうすぐ50歳を迎えます。台湾の家族より今のパートナーと一緒にいる時間の方が長いんです。
「家族」というと血のつながった兄弟や親のことを言うと思います。でも自分の場合は違います。今は僕にとって唯一の家族は同性のパートナーである彼で、これからも欠かせない存在です。ずっとそばにいてほしいと思っています。
Yさん:付き合って25年、お互い気兼ねしないで生活し合っていけることが楽だなと思っています。
今まで好きになった人に対しては「自分が気を使って行動しなければ」というところがあったんですが、彼の場合は見栄を張らずに、自分のネガティブな性格や悪いところも全部受け止めてくれる。だからこそこの関係が続いているのかなと思います。

ずっと一緒にいると、気持ちの甘えからつい雑に扱ってしまうけど、いないといないで寂しくなるんですよね。最近は彼がLGBT関連のイベントにばっかり行って、帰って来るのが遅いので、一人でテレビを見ていて寂しいなと思ったりします。
――お二人の性格は正反対な印象も受けたのですが、むしろ歯車のように合っているのですね。
Yさん:彼が大雑把で、僕が几帳面ですね(笑)。
Gさん:彼はかなり引っ込み思案で、自分はそうでもないのでかなり違いますね。昔から一貫してあまりカッコつけない自然な感じなところが好きですね。
付き合ってから25年全然変わっていないですね。たまに後ろ向きな性格がイラつくこともありますが(笑)。
普段も結構よく口喧嘩をしますし、昔は大きな喧嘩もありました。でもこの関係は切っちゃダメだという思いがずっとあったんです。くされ縁ですかね。

――「結婚」という制度の有無に関らず、お二人の関係は強固なものなんですよね。
Gさん:はい。でも、もし結婚ができたら面倒な手続きもしなくて良いし、権利も得られるんだなと思うと、日本でも早く同性婚が実現してほしいなと思います。
――最後にこれまでの生活や裁判を振り返って率直な気持ちをお聞かせください。
Gさん:在留資格を得ることができてホっとしました。年齢的に遅いかもしれませんが、これからの人生に可能性も出てきて、頑張って生きていかないとと思っています。
Yさん:僕の今一番正直な気持ちとしては「もう少し長生きしようかな…」という思いです。これから二人で堂々と生きていけるんだな、そう思います。
Gさん:(驚いた表情で)今初めて聞きました…!
今まで調書で質問を受けたり、メディアで取材を受けるときに彼は常にマイナス思考だったんですが、今日初めて彼からこんな言葉を聞けました。嬉しいです。

取材後記
GさんとYさんにお話を伺った。違う国、違う年代に生まれ、たまたま日本の新宿二丁目という街で出会った二人が、互いに何の契約もない状態で25年もの時間を共に過ごす。「家族」とは一体何なのか、改めて考えさせられた。
これまで決して平坦な道のりではなかった。取材中にも口喧嘩が始まることもあった。そうかと思うと、互いのことを想い合っていることが伝わってくる場面もあり、二人が気の置けない間柄であること、そのつながりの強さを感じさせられた。
取材の最後にYさんが「もう少し長生きしようかな…」とそっとつぶやいたとき、自分の胸に込み上がる熱を感じた。
「ただ一緒に生きたかった」という一心で今日まで生き抜き、在留特別許可を得ることができたGさんとYさん。お二人のこれからの人生が幸福で溢れることを願ってやまない。

最初に書いた通り、国が国際同性カップルの一方に対して非正規滞在の状態から在留特別許可を与えたのはGさんのケースが日本で初めてだ。その一方で、Gさん以外にも多くの国際同性カップルが今も様々な不安を抱えながら日本で生活している。
例えば、外国人パートナーの方が就労ビザなどを更新し続けることで日本に留まることができていても、仕事を失ってしまった場合は帰らなければならなくなってしまう。日本を離れて別の国で同性婚をし、その国で住み続けるカップルもいる。
同性婚が可能な国で外国人(日本国籍者以外)同士が同性婚をした場合、その一方が何らかの在留資格で来日し、その後パートナーを日本に呼び寄せる場合はパートナーに「特定活動」の在留資格が出る。
しかし、日本では同性婚が認められていないという理由から、同じように外国で同性婚をした同性カップルであっても、日本人と外国人との組み合わせの場合には在留資格が出ないという現実がある。

今年2月14日に「同性カップルが結婚できないことは憲法違反だ」として、全国で国を相手取った集団訴訟が一斉提起された。この同性婚訴訟の原告の中にも数組の国際同性カップルがいる。あるカップルは、一方が留学ビザで来日しているため、就職がうまくいかなかった場合のことを考えると不安だという。
台湾では「同性婚が認められないのは憲法違反だ」という2017年の大法官判断により、今年の5月24日から同性婚が可能になった。さらに世界では26の国と地域で同性婚が認められており、G7で同性間のパートナーシップを保障する法律がないのは日本だけである。
Gさんはこう言っていた。「僕にとって唯一の家族は同性のパートナーである彼で、これからも欠かせない存在です」。
もしGさんとYさんが異性のカップルだったら、あるいはもし日本で同性婚が可能だったら――二人の運命はきっと今とは違うものになっていただろう。日本で暮らす273万人以上の外国人、その中には自分と同じ性の「家族」を持ち、同性婚の法制化によって救われる人たちが、きっとたくさんいるに違いない。