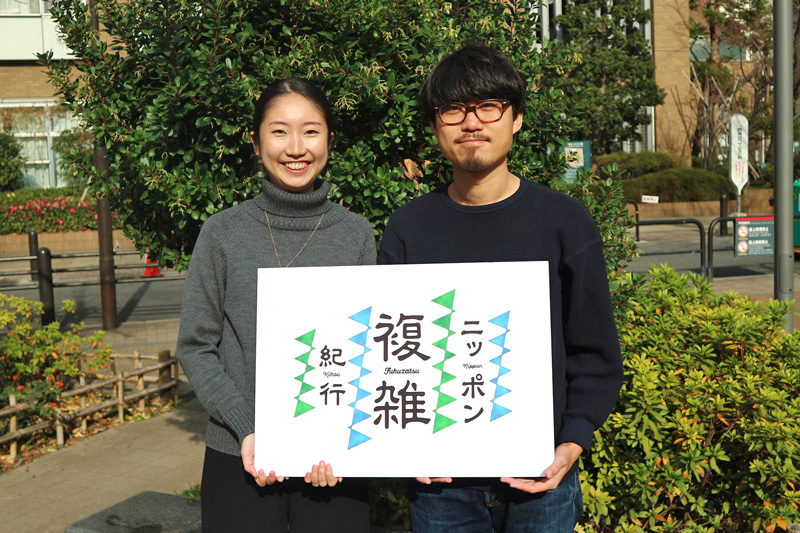2018.03.29
精神障害を持つインドシナ難民たちの最後の拠り所。あかつきの村で今日も紡がれる「ただ共にあること」の意味
群馬にいまだ残る「精神障害を持つインドシナ難民」たちの拠り所
群馬県前橋市東部の赤城山麓に「あかつきの村」という場所がある。この場所では「精神障害を持つ4人のベトナム難民」が、2人の職員、6人の日本人入居者とともに毎日寝食を共にしながら暮らしている。
あかつきの村は1979年に「社会に居場所のない人を受け入れる共同体」として始まった。しかし、その後すぐにインドシナ(=ベトナム、ラオス、カンボジア)からの難民が日本にも数多く訪れたため、それに合わせて村では特に「精神障害を持つ難民」の受け入れを行うようになった。当時から35年以上経った今も、ベトナム人の難民がこの場所で暮らしている所以である。

1982年のベトナム難民受け入れ以降、一時は、アフガニスタンなど様々な国から逃れてきた難民の受け入れも行った。日本が受け入れたインドシナ難民の約8割がベトナム出身だったこともあり、インドシナ難民の中で村が受け入れてきたのは、ベトナム難民のみ。
1975年のベトナム戦争終結以後、社会主義への体制変更による迫害を恐れて多くの人々が「インドシナ」と呼ばれるベトナム、カンボジア、ラオスから海外に逃れた。「インドシナ難民」や「ボート・ピープル」と呼ばれたこうした人々は当時の日本にも流れ着き、日本は約1万1000人のインドシナ難民を受け入れることになった。日本の難民受け入れを大きく変えた出来事だ。
大規模な難民の流入に対して、政府による当初の受け入れ体制は不十分だった。そのため、宗教団体を中心に民間団体が難民のための一時的な滞在施設を作って受け入れに尽力した。あかつきの村もそうした流れの中で、カトリック団体「カリタス・ジャパン」からの要請で村の敷地内に難民定住促進センターを建設することになった。1982年のことである。
このようにして全国にできた約40カ所の民間施設は、インドシナ難民たちが日本社会で一歩を踏み出すための最初の拠り所として位置付けられた。施設に入居した難民は日本語の勉強をしながら働き、その大半は最終的に社会へと出て行くことになった。結果として、90年代の後半にはほとんどの受け入れ施設がその役割を終え閉鎖した。
他方、政府の側でも1979年から83年にかけて全国に受け入れのための施設を順次開設していく。姫路定住促進センター(兵庫県)、大和定住促進センター(神奈川県)、大村難民一時レセプションセンター(長崎県)、国際救援センター(東京都品川区)である。現在は政府のセンターもすべて閉鎖されている。
官民の施設が次々と閉鎖される中、あかつきの村だけはその後も活動を継続した。結果として、現在では精神障害を持つインドシナ難民のための日本に残る最後の受け入れ施設となっている。

私があかつきの村を知ったのは難民支援に関わって間もない7年ほど前のことだ。長く支援に関わる先輩たちから「今後の難民受け入れは、インドシナ難民受け入れの歴史から学ばなければならない」と聞かされ、その中であかつきの村のことも教えてもらった。しかし目の前の実務に忙殺される中、村のことは記憶の片隅に置いたまま時間だけが過ぎてしまった。
ようやく見学に出向いたのは昨年の8月。実際に村を訪れて「インドシナ難民の受け入れは”歴史”ではなく現在進行形である」ということを思った。しかし、実際には当時のインドシナ難民受け入れを覚えている人、その後の経緯に関心を持つ人自体が減ってきているのが現実だろう。
そんな現実を前にして、私の中で「あかつきの村で今も続く取り組みを伝え、記録しなければ」と気持ちが強く揺さぶられた。そして、もう一度あかつきの村を訪れた。

この記事では、あかつきの村に暮らす2人の職員、佐藤さん、櫻井さんのお話を通じて、「あかつきの村とはどういう場所なのか」、「難民を受け入れるとはどういうことなのか」を考えてみたいと思う。
多くの難民たちが自立した後にもなお残った病者に出会い、私はこの村に来た
ーーまずは、あかつきの村に来たベトナム難民の方々の背景を教えてください。
佐藤:初期は南ベトナム政府や軍の関係者が多かったと聞いています。その後、10代、20代の男性も逃れてきました。自分の子どもが徴兵されないようにとの親心でしょう。親が子どもだけを船に乗せて逃がしたケースもあります。子どもたちの視点から見れば、家族と離れ離れで、たった一人、行き先もはっきりわからないまま船に乗せられるという状況だったのではないでしょうか。

佐藤:その一方で、ベトナムが共産圏となり、その政治的な状況を嫌って自らの意思で日本に逃れてきた人たちもいました。どちらかと言うと海外に逃れる目的がはっきりしていた人たちの方が、日本でも割と精神的に頑張れたのではないかと思います。家族が一緒の場合はなおさらですね。
私があかつきの村に来たのは1999年。難民に対する支援の成果が目に見える形でまだあった時代の終わり頃です。目に見えるというのは、彼らが地域で自立していくとか、彼らの子どもが学校に入学するとか、そういう意味ですね。
村が初めて難民を受け入れたのは1982年で、16人のベトナム難民の受け入れがスタートでした。最大で約70人が滞在した時期もあり、これまでの累計で300人ぐらいです。彼らの大半はその後群馬県伊勢崎市など村の周辺にある地域への定住へと移行し、一部は家族再会のためにアメリカなどへと出国していきました。
しかし、そんな風にして多くの難民たちがこの村を去った後にもなおこの村に残された病者がいました。彼との出会いがあって、私はここに来たんです。
とりあえず1年で抜けるつもりで関わり始めた
ーー佐藤さんが村で働くようになったのは「難民の社会的な自立を促す場」から、「精神障害を持ち村に残らざるを得なかった人たちを支える場」へとあかつきの村の役割が変わる過度期だったんですね。櫻井さんはいつ頃からこの村に関わっているんですか?

櫻井:私がここに来たのは障害者自立支援法が施行された2007年です。この法施行で、障害者福祉がこれまでの「措置」から「サービスの提供」へと切り替り、専門的知識に基づいた質の高いサービスを提供する事業になったんです。それで、専門職が必要ということになり、「一年でいいから事業の基礎作りを手伝ってもらえないか」という話をもらったのがきっかけでした。
一通り施設の説明を聞いても、正直、何を言っているのか全然理解できませんでした。まず、自分が外国人の方の支援に関わるとは全く考えたこともなかったですし、ましてや「難民」といわれても、どこか遠くの出来事のように思っていましたから。
それから、精神障害の方々の置かれた状況です。地域生活は難しく、医療機関での入院か治療しかないといえる症状の重さにもかかわらず、病院に行っても言語や文化面で対応してもらえずに村に戻されたという話を聞いて、愕然としました。これまで学んできた世界観にはない「例外」をいきなり目の当たりにしたという状況でした。
それでもとにかくこの場所には難民の中でも精神疾患を持った人が残されていて、その方たちのために丁寧な専門的支援を行わなければならない。しかも創立者である石川神父の体調が非常に悪い状態にある。そういった困難な状況にあることをまずは理解し、1年ぐらいだったらということで始めました。
祖国にも居場所がない。自死を選んだ難民
ーー精神障害の発症は、難民であることと何らか関係しているのでしょうか?
櫻井:実は、日本に来たインドシナ難民が特に精神疾患の発症率が高いという統計はありません。重度といわれる統合失調症を発症した人は日本が受け入れたインドシナ難民約1万人の内100人程度です。これはWHO(世界保健機関)による統合失調症の発症割合である100人に1人と概ね同程度です。ただ、来日後の経験が何らかの引き金となり発症した人は多いようです。


櫻井:戦争で国を追われた難民の人たちは、この先どう生きていけばいいかわからない。日本に来て、3ヶ月ぐらい日本語を勉強して、あとは頑張って仕事をして生きてくみたいな感じで、ポーンと社会へ出されます。職場では日本語がわからず、怒られ、家に帰っても家族はいない、誰も話す相手がいない。そうなると、自尊心が失われて、不安感も増してくる。そうやって、病気になる人が多かったですね。
ーーあかつきの村では、来日から年数が経っても日本社会で新たな帰属意識を持てずに苦しんだ人も少なくなかったそうですね。多くを失い、圧倒的な孤独を抱えて生きる難民にとって「いつか母国に戻る」ことは、数少ない、もしくは唯一の希望であり、日本での孤独に耐えて生き続ける糧だったということでしょうか?
佐藤:日本に来て時間が経っても、まだプカプカ浮いている状態なんですよね、日本とベトナムの間で。「帰りたい、帰りたい」って言うんですよ。実際にここからも数人がベトナムに帰りました。でも、当時のベトナムでは精神医療が遅れていて、家族にお祓いへ連れていかれたり、囲いのある病院に入れられたり。
ベトナムの家族にとっては食い扶持が余計にかかるだけでなく、ベトナムでの制度的な位置づけも「外国人」だから色々と大変。「外国人は医療費が高いから早く連れて帰ってくれ」と言う家族もいました。
それで、多くの人たちは一旦帰国した後に結局日本に戻ってきた。そして、そのあと一年くらいで自殺してしまう人たちもいました。ベトナムに帰国する前は何とかプカプカ浮いていたけど、今度は完全に退路が断たれてしまった。国と家族を失った状態です。ここでは4人が自殺しました。
そんなことが続いてからはもう誰も「帰る」とは言わなくなりました。みんな、たくさんの死を見送って、諦めていったということだと思います。
ーールーツだと思っていた家族や国からも見放されてしまったんですね。
佐藤:ベトナムもまだ今のようには豊かな時代でもないでしょう。家族も食べるので精いっぱいだから。

生きるために必要だったサンさんとの関係
ーー佐藤さんがあかつきの村に住み込むことを決めた理由であり、今も最も長い時間を一緒に過ごしているという「サンさん」について少し教えてくださいませんか。
佐藤:ここで一番重度の精神障害を抱えている人です。10代で単身ベトナムから来日し、今は50代前半。一度帰国しましたが、家族に受け入れてもらえず、今では天涯孤独です。精神科以外の病気になっても受診してくれる病院がどこにもないので、風邪一つ引かせられません。
私が初めて会ったときは本当にひどい状態でした。いつも何かに震えていて人を寄せつけない。床はオシッコまみれ。親が見たら泣くだろうなと思いました。でも、彼に会ったときに、なぜか「憐れ」という思いと同時に「この人は愛されている、私もまた愛されている」と感じたんです。サンさんは、私にとって恩人でもあり、同伴者。この時に癒しを受けました。

ーーサンさんと共に暮らすために「2時間以上は彼の元を離れられない」という生活を送っているそうですが、なぜそこまで彼に尽くせるのですか?
佐藤:理屈じゃないんです。私はそれまで人から受け取るのが当たり前で愛されて育ってきた。ぼんやりと生きてきた。証券会社で働き、バリバリのバブルの子としてスルスル生きてきた。サンさんと出会い、自分を超えて他者を愛することを引き出されたのだと思います。
恵まれて育ってきたけれど、生きていれば自分の内的な苦しさとか渇きとか、色々なものがあるわけですよ。それが、サンさんと出会い、一緒に歩く中で、自分の中の存在肯定感のなさとか、喪失感とか、失ったものを取り戻すことができた感じです。
生産性で言えばマイナスの存在。でも人間にとって何が大切かを教えてくれた
ーー日常生活では色々なお世話をしていても、支援する/される、という関係ではないのでしょうか。
佐藤:サンさんは実際には色々な人の手を借りないと生きていくことができない。生産性でいえばマイナスですよね。お金もかかるし。でも、彼の苦しみを通して、本質的に人は何が大切かということを私は伝えてもらった。
じゃあ、それが「何」なのかということを言葉にしてしまうと、ありきたりになってしまうのですが…。人が生きるということは、生産性とか、モノ・カネだけの話ではない。サンさんを通じて、そういうことを受けた者の責任として、返していく。今もこの村が開かれて人を迎え入れるのは、それを具体的にするということだと思います。それが結果的に、サンさんたちが生きる場を広げていくことにもつながりますし。

ーーモノ・カネだけではない関係性ですね。
佐藤:共産圏から逃れてきた人たちが求める「本当の自由」とは、モノやカネを得るということだけではないんですよね。日本に来てモノを集めれば「もっともっと」となるし、偉くなっていけば「もっともっと」となります。競争社会の原理ですよね。でも、それだけではない。モノ・カネとは違うところにある価値や喜びを知って、幸せを感じられる生活があれば、それは豊かで自由だと思うんです。
ここは宗教的なところから始まっているんですよね。関わってくれるボランティアさんも、モノ・カネの支援だけではなく、関わりの支援でもあるんです。モノ・カネで片付くうちは簡単ですよ。
専門家としての葛藤
ーー佐藤さんがサンさんとの出会いを通じて自らあかつきの村に関わり出した一方で、櫻井さんは当初1年で抜けるつもりだったんですよね。当時はカリスマ的存在の石川神父が不在の中、佐藤さんは7年間孤立奮闘しすでに限界という状況だったと聞きます。櫻井さんが結局1年で辞めなかったのはなぜですか?
櫻井:なし崩し的です(笑)。初めの1年でここで働くことが並大抵のことではないとわかりました。早めに逃げるしかないとも思っていたんですが、とはいえ誰かに渡すにしてもちゃんとした形で渡すべきと思い必死で頑張りました。
結局1年で後任は見つからず、頑張ってきたもののそれで自分の限界を感じてしまったんですよね。直視しないようにしていた本質的な部分が見え隠れしてきて。精神保健福祉士という専門職として関わっていてもあかつきの村の本質的なニーズには寄り添えない、触れられないと。そこに関わろうと思ったら自分の何かを捨てるか何かしなければいけないと。それがすごくきつかったんです。

櫻井:佐藤さんみたいな人が身近にいて、かたや専門職の自分には職域があり、まず自分の身を守ることから考える。専門職としての倫理観にも煩わしさを感じていて、結局専門家として何の役に立つのか、ここに来てずっと考えてきたんですよね。
ただ一緒に生活する。ただそばにいる。それがこの村に必要なこと。そこに、あかつきの村の本質がある。それがわかってしまってから、やっぱりもうこれ以上続けられない、辞めたほうがいいって思ったんです。
それで、2011年に辞表を出しました。
ーーそうだったんですね…。
櫻井:でも周りにうまいこと言われて、結局辞められませんでした…(笑)。
転機は「何歳で結婚するんだ?」と聞かれなくなったこと
ーー辞表撤回後はどうだったんでしょうか?
櫻井:頭のねじが取れました(笑)。それまでは毎日村の外から通っていたんですが、中途半端じゃダメだと思って住み込むようにしたんです。そうしたら難民の人たちとの関係が変わってきて。
村に住み込む前は、難民の人たちから毎日のように「ひろきさん、何歳で結婚するんだ?」、「家族は元気か?」と聞かれていたんですね。そのときは「そんなこと知らねぇよ。昨日と変わんねぇよ。なんで毎日こんなこと聞くんだろう…」と思っていました。でも、村に住み込むようになってからそういう質問をされなくなったんです。

櫻井:ある日、退職する職員を見送るときのみんなの様子を見ていてその質問の意味に気づいたんです。
「何歳で結婚するんだ?」と聞くのは、「お前もいつかこの村からいなくなるんだろう?」って意味だったんですね。結婚したり、両親が病気になったりしたら、ここで働いている人たちは離れていってしまう。ここにいる難民の人たちは常に見送ってきた側なんだなと。
昔は70人くらいの難民の人たちが一緒に生活をしていて、人気があって、安心感にいつも触れながら生活していた。でも、皆どんどんここから出て行くんですよね。その変化をここに残る難民の人たちはずっと経験してきた。
そして、自分はそういう質問をされなくなったんです。あーなんか、こういうことなのかな、って。
ーーつまり、受け入れられた…。
櫻井:共に「いる」というか、共に「ある」という感じ。自分の存在がやっとあかつきの村の本質的な部分に少し触れることができたのかもしれないなとそのとき思いました。
人の生き死に関わる本質を教えてくれた難民の存在
ーー宗教的な考え方で支えられているあかつきの村で、非カトリックの櫻井さんが暮らし続けることは決して簡単ではないと感じます。何が櫻井さんを今に至るまでここに留まり続けさせているのでしょうか?
櫻井:やはりベトナム難民の障害者の人たちの存在ですね。ここに来るまで僕は恥ずかしながら難民の人たちが日本にいることすら全然知りませんでした。
難民の人たちはいつも言うんです。「自分は家族も誰もいない。結婚もできないし、仕事もできない。ずっとここにいるだけ、ただここで死ぬのを待ってるだけ」と。
笑いながら言うから、始めは冗談だと思っていました。ただ、ある時外で一人でタバコを吸っていた方のあまりに寂しい表情を見て、今まで感じたことのない圧倒的な孤独感が伝わってきました。

櫻井:精神疾患を抱えていても、生活保護などの制度で経済的にはとりあえず生きていくことができる。あかつきの村という居住の場もある。だけど、そういう物質的なことだけでは満たされない何か、生き死に関わるような何かが満たされていないんだなと感じたんです。難民たちの話を聞いて。
人間が精神を病むということは、自分が壊され目に見えない苦しさが続くということ。言い換えるとアイデンティティの揺らぎともいえます。その揺らぎを埋めてあげられるのが他者。
人との関わりの中でしか癒されない部分ってありますよね。自分の物質的欲求が満たされるのではなく、単純に人との関わりみたいなものが満たされているだけで幸せを感じられる。みんなを見ているとそう思うんです。

村を開くことで迷惑をかけるかもしれない。でも、開くことで誰かが助けてくれる
ーー村の入り口は門がなく誰にでもオープンです。精神障害を持つ人たちがいる施設を開放することについてはどう考えていますか?
佐藤:施設を開放することで地域に迷惑をかけたこともありました。でも、地域が受け止めてくれたんですね。摩擦や衝突はあるけど閉じられているよりいい。入居者それぞれが学びながら、地域の人たちと関わる上での対応力を身につけてきた。
開くことで誰かが助けてくれる。この地域にここを手伝ってくださるシスターの方々が住んでくれたことも大きいです。
櫻井:常にいろんな人が出入りしています。職員もここに住んでいるから、地域からは住人として認知されている。障害者施設と思っている人は少ないと思います。

ーーあかつきの村を今後どうしていきたいというのはありますか?
佐藤:活動は、人が先でしょ。村の手作りの建物を見ればわかるようにハードも絶えず変えてきました。誰がこの村を引き受けるかによって、その人が表現していく形になる。
だから、櫻井さんが責任者になったとき、次の時代の形はなんでもよいと思ったのよね。一番大事なことは、誰もが生きられる場を作ること。障害者とかにこだわって狭めるのではなく。
櫻井:そうですね、こだわらない。こだわりがマイノリティを作ってしまうから。障害者だけでなく、高齢者や社会的なマイノリティ、そういう人たちと一緒に仕事ができる場、地域の共同作業所のような感覚は、あかつきの村の変わらない特徴であり続けると思います。
ーー佐藤さん、櫻井さん、貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。
取材を終えて
あかつきの村を一言で伝えることは難しい。「難民」「障害者」「信者」「専門家」など、さまざまなカテゴリーの人たちが、カテゴリーを超えた関係を築きながら、共存している。
一歩足を踏み入れると「自分がちゃんと生きているか」を問われているような緊張感があった。だから単純に「居心地が良い」とも言い切れない。でも、よそ者にもオープンで、ついつい長居をしたくなる。あかつきの村はそんな不思議な場所だった。
支援の観点からあかつきの村をとらえると、佐藤さんと櫻井さんの取り組みには同じ支援業界に関わる者としてただただ圧倒される。サンさんのような自立のめどが立たない人を制度で救うことは難しい。組織として活動している支援団体が関わるには相当の覚悟とコミットが必要である。
そんな「支援の隙間」を埋めているのが村の存在であり、それを可能にしているのがあかつきの村の「本質」だと思う。それを、佐藤さんは「モノ・カネではない関係」、櫻井さんは「人との関わり」と表現してくれた。一見「普通」ではない村の営みは、互いの違いから過度な分断や摩擦が起きている現代をどう生きるのか、私たちにヒントを与えてくれているように感じた。
あかつきの村にある関係性は、私たちの身の回りにも大なり小なり存在するだろう。もし、そんな関係性を社会にもう少し増やすことができたら、難民もそうでない人も、もう少しは生きやすい社会になるのではないだろうか。難民受け入れの形を考えることを通じて、結局、受け入れる社会の側がどんな社会でありたいかということが問われているのだと思った。
Credit
田中志穂|取材・執筆
望月優大|取材・編集
宮本直孝|写真
ーーーーー
記事をお読みくださった皆様へ。ニッポン複雑紀行は認定NPO法人難民支援協会が運営するウェブマガジンで現在クラウドファンディングを実施しています(2019年2月14日まで)。持続的な運営のために以下のリンクよりぜひご支援いただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。